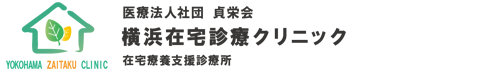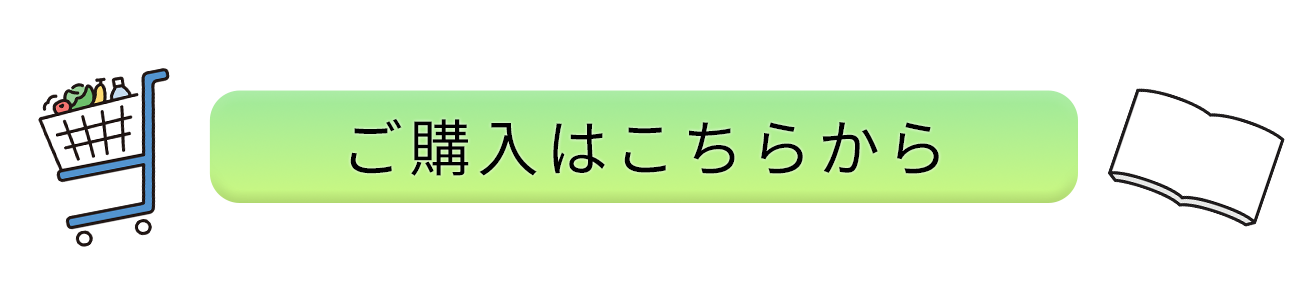終末期だけではない、生活を支える在宅医療
在宅医療というと、「がん患者さんが終末期に利用するもの」と思っている人も多いかもしれません。
実際にがんの患者さんでは、病院で手術や抗がん剤治療を受け、病院の治療を終えたところで、残る時間は自宅でゆっくりと過ごしたいという希望で在宅医療に移行するケースが多々あります。
そのような利用の仕方もいいのですが、在宅医である私からすれば、治療中から在宅医療を検討していただくといいと思っています。現在は、疼痛を和らげる緩和ケアや一部の抗がん剤治療を在宅でも行えるようになっているからです。
在宅医療で対応できるがんの緩和ケアには、次のようなものがあります。
実際にがんの患者さんでは、病院で手術や抗がん剤治療を受け、病院の治療を終えたところで、残る時間は自宅でゆっくりと過ごしたいという希望で在宅医療に移行するケースが多々あります。
そのような利用の仕方もいいのですが、在宅医である私からすれば、治療中から在宅医療を検討していただくといいと思っています。現在は、疼痛を和らげる緩和ケアや一部の抗がん剤治療を在宅でも行えるようになっているからです。
在宅医療で対応できるがんの緩和ケアには、次のようなものがあります。
- 疼痛対策(麻薬使用) 適切に麻薬を使い、痛みを取り除きます。麻薬には内服薬や座薬、貼付薬、注射などのさまざまなタイプがあります。
- 在宅酸素療法 慢性呼吸不全や心不全などがあるときは、在宅酸素療法を行います。専用の装置やボンベから酸素をチューブで吸入します。
- 胃ろうなどの経管栄養 胃に専用の穴をあけ、そこから栄養を入れるのが胃ろうです。鼻から消化管にチューブを入れ、栄養を送る経鼻経管栄養もあります。
- 中心静脈栄養 静脈の血管に、高カロリー輸液を投与するものです。消化管の機能が落ちている人でも栄養を摂ることができます。
- 胸水、腹水の除去
さらに、がんの患者さんのQOL(Quality of Life:生活の質、人生の質)の点でも、早めに在宅医療を利用してほしいと思います。
病院でギリギリまで治療をして亡くなる前の数週間だけ自宅で過ごすというのは、せっかく自宅に戻っても、自分の好きなことをする時間や、家族や親しい人との時間を楽しむことができません。
また、早くから在宅を併用して在宅医療チームと信頼関係をつくっておくと、看取りについての方針や患者さん・家族の希望について、十分に話し合うことができます。数週間という短期間では、それができないまま最期に至ることもあります。
ですから、終末期のためというより、安心して治療に取り組むためにも在宅医療を活用してください。
病院でギリギリまで治療をして亡くなる前の数週間だけ自宅で過ごすというのは、せっかく自宅に戻っても、自分の好きなことをする時間や、家族や親しい人との時間を楽しむことができません。
また、早くから在宅を併用して在宅医療チームと信頼関係をつくっておくと、看取りについての方針や患者さん・家族の希望について、十分に話し合うことができます。数週間という短期間では、それができないまま最期に至ることもあります。
ですから、終末期のためというより、安心して治療に取り組むためにも在宅医療を活用してください。
紹介状から読み取れる、在宅医療に入るまでの物語
現在の在宅医療では、病院に通院・入院をしたことがない人が、いきなり在宅医療で治療を行うという例はごくまれです。やはり病院でいろいろな治療を受けていたり、入退院を繰り返し、紆余曲折を経てようやく在宅医療にたどり着いた人が多いのが現状です。
そこで当クリニックでは、病院や地域の医師からの紹介で在宅医療を始める人の最初に接するときは、事前に紹介状をじっくり読み込むというプロセスを重視しています。
それまで病院で治療をしていた人が、在宅医療に移行するときには、本人にも家族にもさまざまな不安、葛藤があるものです。
病院での治療を諦めていいのか、病院の主治医との関係はどうなるのか、在宅ではどんな療養生活になるのか、終末期や看取りを覚悟すべきなのか。自分や家族の命に関わる難問を前に、「この選択でいいのか」と迷っている人が大半かもしれません。
そうした患者さんや家族の心情に寄り添うためには、これまでの経緯が記された紹介状を、よく読む必要があります。
紹介状から、病院での治療をサポートするための在宅医療ということがわかれば、在宅医療チームから患者さんに掛ける言葉は「一緒にこれから頑張っていきましょう」となります。一方、長く入院していた人が、もう治療はいいから、家でゆっくり過ごしたいと在宅療養を始めるときは、「今までよく頑張りましたね、お帰りなさい」という言葉になります。
医療従事者が紹介状で病気の経過だけを見るのではなく、入退院を繰り返すなど、苦労して治療をされてきた物語に思いを寄せることで、本人やご家族も安心して在宅医療に踏み出すことができます。
そこで当クリニックでは、病院や地域の医師からの紹介で在宅医療を始める人の最初に接するときは、事前に紹介状をじっくり読み込むというプロセスを重視しています。
それまで病院で治療をしていた人が、在宅医療に移行するときには、本人にも家族にもさまざまな不安、葛藤があるものです。
病院での治療を諦めていいのか、病院の主治医との関係はどうなるのか、在宅ではどんな療養生活になるのか、終末期や看取りを覚悟すべきなのか。自分や家族の命に関わる難問を前に、「この選択でいいのか」と迷っている人が大半かもしれません。
そうした患者さんや家族の心情に寄り添うためには、これまでの経緯が記された紹介状を、よく読む必要があります。
紹介状から、病院での治療をサポートするための在宅医療ということがわかれば、在宅医療チームから患者さんに掛ける言葉は「一緒にこれから頑張っていきましょう」となります。一方、長く入院していた人が、もう治療はいいから、家でゆっくり過ごしたいと在宅療養を始めるときは、「今までよく頑張りましたね、お帰りなさい」という言葉になります。
医療従事者が紹介状で病気の経過だけを見るのではなく、入退院を繰り返すなど、苦労して治療をされてきた物語に思いを寄せることで、本人やご家族も安心して在宅医療に踏み出すことができます。
ちなみに:在宅医は「紹介状」のここを見る
別の病院・クリニックで治療を受けていた人が在宅医療に切り替えるときに、非常に重要な情報源となるのが、「紹介状」です。病院の医師と在宅医では、この紹介状の見方も異なります。
病院の医師が紹介状で見るのは、いつ、どこでどんな治療を受けたか、どんな薬を使ってきたか、といった病気の治療内容や経過です。いわば、その病院での治療方針を決めるための情報確認、という意味合いが強いと思います。
それに対して在宅医が見るのは、病気のことだけではありません。これまでの治療内容や経過も無論、重要ですが、さらにその背景にある患者さんとご家族の歴史というか、“本人・ご家族の物語”を読み取ることがとても大切になります。
例えば、5年もがんの治療をして苦労をされてきたんだな、つらい思いもしただろうし、本人もご家族も悩んだだろう。そういう患者さんやご家族の1つひとつすべて異なる物語に思いをはせ、「自分だったら」「自分の家族だったら」と想像力を働かせてみるのです。
そうすることで初めて、患者さんやご家族の思いを理解できるようになりますし、そのうえで「この人たちの生活を支えるために何が必要か」という、在宅の治療方針を考えることができます。
病院の医師が紹介状で見るのは、いつ、どこでどんな治療を受けたか、どんな薬を使ってきたか、といった病気の治療内容や経過です。いわば、その病院での治療方針を決めるための情報確認、という意味合いが強いと思います。
それに対して在宅医が見るのは、病気のことだけではありません。これまでの治療内容や経過も無論、重要ですが、さらにその背景にある患者さんとご家族の歴史というか、“本人・ご家族の物語”を読み取ることがとても大切になります。
例えば、5年もがんの治療をして苦労をされてきたんだな、つらい思いもしただろうし、本人もご家族も悩んだだろう。そういう患者さんやご家族の1つひとつすべて異なる物語に思いをはせ、「自分だったら」「自分の家族だったら」と想像力を働かせてみるのです。
そうすることで初めて、患者さんやご家族の思いを理解できるようになりますし、そのうえで「この人たちの生活を支えるために何が必要か」という、在宅の治療方針を考えることができます。